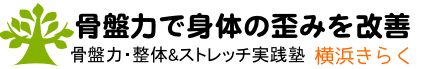ひな祭り
江戸時代までは和暦(太陰太陽暦)の3月の節句(上巳、桃の節句)である3月3日(現在の4月頃)に行われていました。
明治の改暦以後は一般的にグレゴリオ暦(新暦)の3月3日に行なうことが一般的になりました。
旧暦の3月3日は桃の花が咲く時期であるため「桃の節句」と呼ばれることが多いです。
その起源説は複数あり、平安時代の京都で既に平安貴族の子女の雅びな「遊びごと」として行われていたとする記録があります。
初めは儀式ではなく遊びであり、雛祭りが「ひなあそび」とも呼ばれるのはそのためです。
一方、平安時代には川へ紙で作った人形を流す「流し雛」があり、「上巳の節句(穢れ払い)」として雛人形は「災厄よけ」の「守り雛」として祀られる様になりました。
母から娘へ
我が家の雛人形は妻が生まれた時に買ってもらった物です。
そして娘へ。
寿司ケーキ
ちらし寿司に見えますかね?
デコレーションちらし寿司?
寿司ケーキですかね、これも妻の作。
お顔は、娘の作です。

ケーキ
こちらは、本当の手作りケーキ。